21悽婭偵偍偗傞婋婡偲攋嬊偵懳偡傞恀惈妶惈抦偺栶妱 |
|
|
|
丂丂丂丂
丂丂丂丂戞堦復丂妶惈抦偲偼壗偐
丂丂丂丂戞擇復丂抦揑塩堊偺杮幙
丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮抦偺巌椷僗僥僀僩丄婍夿抦丒恖娫抦丄曄懱妶惈抦丒恀惈妶惈抦摍偺栤戣偲
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂抦幆偺悽奅娤揑惈幙媦傃垽抦揑惈幙乯
丂丂丂丂戞嶰復丂20悽婭偵傒傞幮夛揑嫵孭偲妛栤忋偺嫵孭
丂丂丂丂戞巐復丂21悽婭偵偍偗傞婋婡偲攋嬊偵懳偡傞妶惈抦偺栶妱
丂丂丂丂 |
|
|
|
丂抦偺暘愅偵偍偄偰偼丄偟偽偟偽丄抦偑宱尡偵傛傞傕偺偱偁傞偐丄宍幃揑偵惉傝棫偮傕偺偱偁傞偐丄偁傞偄偼偦偺杮幙偑偦偺偳偪傜偵傕懏偝側偄揰偵偍偄偰擣傔傜傟傞偐偳偆偐偑栤傢傟傞丅偦偟偰抦偼捈姶揑側惈幙偁傞偄偼傾僾儕僆儕側惈幙傪帩偮傕偺偱偁傞偐偳偆偐偑栤傢傟傞丅壛偊偰丄杮幙傗幚嵼傗恀棟偲偺娭學傪栤傢傟傞偙偲傕偟偽偟偽偱偁傞丅傕偪傠傫丄巹払偼丄抦偺幮夛揑惈奿傗楌巎揑惈奿丄抦偲擣幆偺娭學丄偁傞偄偼崻尮抦乮僔僃儕儞僌)丄埫栙抦乮M.億儔僯乕乯丄媄弍抦丄幚慔抦丄妛峑抦摍乆丄抦幆偵娭偡傞條乆側栤戣傪採弌偟偰榑媍偡傞偙偲偑偱偒傞丅
丂巹偑懆偊傞抦偼丄偦傟傜偺栤戣偲娭傢傜側偄傢偗偱偼側偄偺偩偑丄巹偼丄抦傪恖娫偺妶摦偲偟偰丄摿偵摢擼偺妶摦傪拞怱偵悩偊偰峫嶡偡傞偺偱偁傞丅懄偪丄椡摦揑偱壜擻惈偺朙偐側抦偺夝柧偼丄恖娫偺嵟傕廳梫側婎杮揑偁傝曽偵寢傃偮偒丄恖娫偺摢擼妶摦傗恎懱妶摦偺儊僇僯僘儉偲偺嫮偄娭傢傝偵偍偄偰堊偝傟傞昁梫偑偁傞偲偄偆偙偲側偺偱偁傞丅偙傟偐傜丄偦偺堄枴偱偺抦丄摿偵妶惈抦偲巹偑屇傇抦偺杮幙偲摥偒傪捛偭偰傒傛偆丅
丂堦斒偵丄姶妎婍姱乮sense organ 乯偺偡傋偰偼丄恎懱揑悽奅偺嵟愭抂偵偍偄偰丄偦傟傜偑愙偡傞悽奅偵奐曻偝傟偰偄傞丅偦偺偙偲偵傛偭偰惗柦懱偼丄帺屓偺惗懚偵娭傢傞嵟傕婎杮揑側忣曬傪摼傞偺偱偁傞丅廬偭偰丄姶妎婍姱偲悽奅乮娐嫬乯偺愙怗偼丄恖娫偺抦幆傪峫嶡偡傞忋偵偍偄偰丄嬌傔偰廳梫側婎慴揑僥乕儅偱偁傞偲峫偊側偗傟偽側傜側偄丅摿偵丄旂晢揑姶妎偼丄傑偝偟偔惗柦偺堐帩偁傞偄偼惗巰偵偐偐傢傞傕偺偲偟偰丄偁傜備傞姶妎婍姱偺嵟廳梫側抧埵傪愯傔偰偄傞丅椺偊偽宱尡榑幰偨偪偼丄夣丒晄夣偺栤戣傪榑偠偨偑丄姶忣傪惗偠偝偣傞婎掙偵偁偨傞晹暘偵旂晢姶妎偑偁傞偙偲傪梷偊偰偍偔偙偲偼丄恎懱偲怱偺娭學傪夝偔忋偱傕丄惗柦偺杮幙傪扵傞忋偱傕寛偟偰寉帇偡傞偙偲偺偱偒側偄廳梫側億僀儞僩偱偁傞丅乮拲侾乯
丂恖娫偵尷傜偢丄晄夣偵懳偟偰偼丄摝傟傞偐変枬偡傞偐摤偆偐丄庴偗擖傟傞偐姷傟傞偐曄妚偡傞偐丄偦傟傜偺慖戰傪敆傜傟傞丅恖娫偼丄恎懱揑側柺偩偗偱側偔丄惛恄揑側柺偵偍偄偰傕丄慡懱偲偟偰嫮偔鐥偟偔惉挿偟側偗傟偽側傜側偄惗暔偱偁傞丅廬偭偰丄変乆偼丄偦傟傜偺慖戰傪揔愗偵峴偭偰惉挿偟側偗傟偽側傜側偄丅傕偪傠傫恖娫傕惗暔偲偟偰帺傜偺夣偵岦偐偍偆偲偡傞偐傜丄晄夣偵懳偟偰偼揔愗側慖戰傪峴側偄偨偄丅偱偁傞偐傜丄抦偺栤戣傪扵傞偲偒丄巹払偑抦偲恖娫偺姶妎揑妶摦傗姶忣偲偺娭傢傝傪懆偊傛偆偲偡傞偙偲偼丄抦傪恖娫偺妶摦偲偟偰攃埇偡傞戞堦曕偲側傞偺偱偁傞丅
丂偦偙偱丄愭偢姶妎嵽乮sense datum 乯偑懆偊傞奜晹偺忣曬偐傜巒傔傛偆丅偦傟偑抦揑娭楢偺忣曬偱偁傞応崌丄偦傟傜偑偄偐偵恖娫偺撪晹偵庢傝擖傟傜傟傞偐傪峫嶡偡傞偺偼丄戝曄嫽枴怺偄丅
丂偄偐側傞忣曬傕姶妎婍姱傪捠偠偰庢傝偄傟傜傟傞丅椺偊偽暥帤忣曬偵偍偄偰丄帇妎偺晄帺桼側恖偼丄挳妎傗怗妎傪摥偐偣丄壒惡傗揰帤偵傛偭偰偦偺忣曬傪摼傞偙偲偑弌棃傞丅姶妎婍姱傪捠偠偰摼傜傟傞怣崋偼丄掞峈偺側偄傕偺偐丄寈夲偟偨傝丄嫅斲偟偨傝丄愊嬌揑偵庴偗擖傟偨偄傕偺偐摍偺敾抐傪丄擼偵峴側傢偣傞丅傗偗偳傪偡傞傛偆側擬偄傗偐傫偵怗傞偙偲偼扤傕峴側傢側偄偑丄擬偄僐乕僸乕偼堸傓丅僈僗偺廘偄偼変乆偵婡晀側峴摦傪懀偡偑丄僴乕僽偺崄傝偼変乆傪旕忢偵棊偪拝偐偣傞丅
丂椺偊偽偙偙偵僩儖僗僩僀偺傾儞僫僇儗乕僯僫偑偁傞丅僩儖僗僩僀偼扤偐丅嶌壠偩丅偳偙偺丄偄偮偺丠丂偙偆偟偨栤偄偵懳偡傞夝摎偼丄斵偺嶌昳傪撉傕偆偲偡傞恖偺摦婡偺堦晹傪扴偭偰偄傞偩傠偆丅偦偟偰斵偺柤傪暦偄偨偩偗偱丄恖偼偁傞姶忣傪書偔偱偁傠偆丅傕偟丄壗傕姶偠側偄偲偡傟偽丄偦傟偼姶偠傞傎偳偺抦幆傗宱尡偑側偄偲偄偆偙偲側偺偱偁傞丅偙偺傛偆側偁傝傆傟偨帠椺偐傜丄巹払偼抦幆偲姶忣偵娭楢偑偁傞偲偄偆偙偲傪擣傔丄峫嶡傪怺傔側偗傟偽側傜側偄丅
丂忣曬偼堦偮偺怣崋偲偟偰憲傜傟偳偙傊峴偔偺偐丅擼偱偁傞丅偱偼擼偱偳偆側傞偺偐丅偙偙偱偼丄尵岅忣曬傪庢傝忋偘偰峫偊偰傒傞丅
丂僜僔儏乕儖乮Ferdinand de Saussure乯偵傛偭偰丄婰崋乮signe)偑僔僯僼傿傾儞乮signifiant乯偲僔僯僼傿僄(signifie)偱峔惉偝傟傞偙偲偑巜揈偝傟偨偑丄偙傟偼尦傛傝僗僩傾攈偺婰崋榑乮semiology)傪傾僂僌僗僥傿僰僗偑傑偲傔丄僗僐儔揘妛幰偵傛偭偰庴偗宲偑傟偰偒偨尒曽丄懄偪婰崋乮signum乯傪抦妎憡偱偁傞僔僌僫乕儞僗乮signans乯傗椆夝憡偱偁傞僔僌僫乕僩僁儉(signatum乯偵暘偗傞婰崋榑傪揱摑揑偵庴偗偰偄傞偲峫偊偰傛偄丅儎僐僽僜儞乮Roman Jakobson乯偼丄偄偐側傞尵岅暘愅傕丄傑偨堦斒偵偄偐側傞婰崋暘愅傕丄偦偟偰暘夝偝傟偨暋嶨側婰崋揑扨埵偺媶嬌偺傕偺偱偝偊傕擇廳偱偁傝丄偙偺憃曽傪偲傕偵娷傫偱偄側偗傟偽側傜側偄偟偰偄傞丅乮拲乯偙傟傪抦幆偺栤戣偲娭楢晅偗偰懆偊捈偟偰傒傛偆丅
丂恖娫偺擼偺撪晹偱偼丄婰崋側偄偟扨岅傗尵岅偑丄恖娫偺姶惈傗姶忣偲側傫傜偐偺娭學傪曐偭偰偄傞丅偁傞偄偼丄偦傟傜偼恖娫偵偲偭偰偼丄偦偺恖側傝偺僀儊乕僕傪敽偭偰懚嵼偡傞丅姶惈媊憡(sensitive丂significativeness)偲屇傇偙偺僀儊乕僕偼丄姶惈偱庴偗傜傟偨姶忣柺偑婰崋偵晅梌偝傟偰偄傞偙偲傪帵偡偺偱偁傞丅偦傟傜偑抦揑惈幙傪帩偮抦幆偱偁傟偽丄偦傟偵敽偆僀儊乕僕偼恖偵傛偭偰戝曄暋嶨偱墱峴偒偺偁傞傕偺偵側偭偰偍傝丄摨帪偵懠偺抦幆梫慺偲偮側偑傞宊婡傪桳偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅
丂抦幆偼丄擼偺摿暿側摥偒偺嶌梡偺寢壥偲偟偰惉棫偡傞偲峫偊傜傟傛偆丅偦偺嶌梡傪峫偊偰傒傞偵丄怣崋偲偟偰憲傜傟偰偔傞抦幆梫慺偼丄抦幆偵姶惈媊憡傪梌偊傞旕尵岅揑捈懺乮tacit nonlinguistic fugures)傪捠夁偟丄偦偺偙偲偵傛偭偰丄庴偗庢傜傟偨傕偺偼愭偢婎懱儗儀儖偱偺敾掕傪庴偗傞偺偱偁傞丅偙傟偼惗暔揑忣曬張棟夁掱偱偁傞偑丄傕偆彮偟棟夝傪恑傔傛偆丅懄偪抦幆偼惛恄偺摥偒偺拞偱婡擻揑偵懚嵼偡傞偲峫偊傜傟傞偐傜丄旕尵岅揑捈懺傕堦偮偺婡擻偲尒傜傟傞丅偙偺婡擻偵偼暋嶨偐偮懡條側姰惉偑敪払偟偰偍傝丄偦傟偼宱尡傗抦幆偵寢傃偮偄偰偄傞丅偟偐傕尵岅偵寢傃偮偔偩偗偱側偔丄峀偔條乆側僀儊乕僕偲婰壇偵寢傃偮偔偲峫偊偰傛偄丅椺偊偽壒妝揑僀儊乕僕傗奊夋揑僀儊乕僕丄岝宨偺婰壇側偳傕丄偙偺旕尵岅揑捈懺偺妶摦傪昁梫偲偟丄曐帩偝傟傞偺偱偁傞丅
丂旕尵岅揑捈懺偺栶妱傪妋擣偟偨偲偙傠偱丄怴偨側抦幆梫慺偑怣崋偲偟偰憲傜傟偰偔傞応崌傪専摙偟傛偆丅堦斒偵怴偨側抦幆梫慺偼丄壗偺宍幃傕婯惂傕側偟偵傔偪傖傔偪傖偵擖傝偙傫偱偒偰彑庤偵婛懚偺抦揑梫慺偵傇偮偐傞棎朶幰偱偼側偄偐傜丄揔愗側抦揑梫慺傪庢傝弌偡偨傔偵丄弌崌偄偺応乮婡擻乯傪帩偮昁梫偑偁傞丅偦偺堄枴偱丄巹偼丄旕尵岅揑捈懺偺昞憌晹偵偁偭偰怣崋傪攠夘偡傞憌乮figure乯傪擣傔丄儃儎乕儞乮buoyant乯偲屇傫偱偦偺栶妱傪帵偡偙偲偵偟偰偄傞丅
丂椺偊偽丄將偑帺暘偺柤慜傪屇偽傟偨傝丄巜帵傪梌偊傜傟偨傝偟偰偦傟偵斀墳偡傞応崌偲丄恖娫偲傪斾傋偰傒傟偽丄尵岅偑壥偨偡堄媊偲婡擻偼丄恖娫偵偍偄偰偢偭偲暋嶨偱偁傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅偟偐偟丄恖娫偵偍偄偰傕丄尵岅偺栶妱傗婡擻偑丄幚嵺忋恖偵傛偭偰戝曄側憡堘傪帩偭偨傕偺偲偟偰偁傞偲偄偆偙偲偼擣傔偞傞傪摼側偄丅偦偺恖娫偺怑嬈傗愱栧偵傛傞憡堘偲偼暿偵丄摿偵峫椂偡傋偒偙偲偼丄儃儎乕儞偑屚傟偨忬懺偱偁傞偐丄妶偒妶偒偲偟偨椼婲忬懺乮generation乯偵偁傞偐偳偆偐偲偄偆栤戣偱偁傞丅懄偪丄旕尵岅揑捈懺偺撪梕偑朙偐偱偁傝丄庒乆偟偗傟偽丄儃儎乕儞傕椼婲偟偰偍傝丄旕尵岅揑捈懺偐傜揔愗側楢嵔傪摫偄偰偔傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆揰偵栤戣偑偁傞丅椺偊偽丄儃儎乕儞偺屚傟偨忬懺偱偼丄旕忢偵昻偟偄姶惈媊憡傪岦偐偄崌傢偣傞偟偐側偔丄偦偺楢嵔惈傕搑愗傟偨傕偺偵側偭偰丄懠偺抦幆梫慺偵岦偐偄崌偆椡傪傎偲傫偳摼傞偙偲偑側偄丅旕尵岅揑捈懺偑昻偟偄傕偺偵側偭偰偄傞偲傕尵偊傞偩傠偆丅
丂師偵恑傕偆丅壒偲堄枴偺憃曽偱恖娫偵庴偗偲傔傜傟丄妶梡偝傟傞尵岅婰崋偵姶惈媊憡偑梌偊傜傟傞偲丄偦傟偼夛壇乮co-generative figure乯偲偟偰巆偝傟傞丅夛壇偼丄姶惈媊憡偺懠偵丄帠幚偺斀塮偲偟偰偺梫慺傪帩偭偰抦幆壔偡傞丅廬偭偰乽斀塮榑乿傪抦幆偺栤戣偱榑偠傞応崌偵偼丄抦幆偑夛壇忬懺偵偁偭偰丄僀儊乕僕揑側姶惈媊憡偲尵岅揑婰崋偑崌懱偝傟偰偄傞偙偲傪峫椂偟側偗傟偽側傜側偄丅偲偙傠偱丄尰戙偺擼惗棟妛偱偼丄姶惈媊憡偼塃擼丄尵岅揑婰崋偼嵍擼偱埖傢傟傞偲偄偆偙偲偑敾柧偟偰偄傞丅擼惗棟妛偵傛偭偰摼傜傟偨偙偺惉壥偼丄巹偺媍榑偵懳偡傞丄壢妛揑丄惗棟妛揑側僸儞僩偲崻嫆傪梌偊偰偄傞偺偱偁傞丅
丂夛壇忬懺偺桪傟偨抦幆偼妶惈壔乮generate乯偟丄戲嶳偺懠偺抦幆梫慺偲暋嶨側僱僢僩揑楢嵔傪曐偭偰婡擻揑偵懚嵼偡傞丅偦傟傪妶惈抦乮generative knowledge)偲偄偆偺偱偁傞丅斀懳偵丄懠偺抦幆梫慺偲梋傝寢傃晅偗側偄偐丄摿掕偺傕偺偵偟偐斀墳傪帵偝側偄抦幆傕偁傞丅椼婲偟偰偄側偄偙傟傜偺抦傪暵嵡抦乮ungenerative blocked knowledge乯偲偄偆丅
丂恖娫偼暵嵡抦傪岲傑側偄偑丄嫮惂偝傟偨傝丄帋尡偵戙昞偝傟傞傛偆偵丄偦傟傪庢傝擖傟傞傋偒偁傞栚揑傪梌偊傜傟傞偲丄暵嵡偟偨抦幆傪庢傝擖傟偰偟傑偆丅偦偺帠忣傪峫椂偡傞偲丄抦幆偵偼奜揑摦婡偱庢傝擖傟傜傟傞懁柺偺偁傞偙偲傕尒棊偲偣側偄丅椺偊偽丄暯曽崻偺悢抣傪100寘傑偱妎偊偨幰偑偁傞偲偟傛偆丅斵乮斵彈乯偑傕偟偦傟傪斲墳柍偟偵妎偊偝偣傜傟丄偟偐傕壗偺曬廣傕摼傜傟側偄偲偟偨傜丄偙偺婰壇偼擼傊偺戝偄側傞晧扴偱偟偐側偄丅斀懳偵丄偦傟偑帺暘偺婰壇椡傊偺帋偟傗帺怣偲偟偰帺庡揑偵婰壇偝傟丄偟偐傕偦傟傪廃埻偺恖乆偑姶怱偟偰偔傟傞偲側偭偨傜丄偦偺婰壇忣曬偼夣姶傪敽偭偰偄傞偐傜擼傊偺晧扴偵偼側傜側偄偱偁傠偆丅傕偪傠傫偙偺庬偺婰壇忣曬偼丄堦偮偺悢妛忋偺栺懇傗朄懃偺拞偱妶梡偝傟傞宊婡傪帩偭偰偄傞丅偟偐偟丄暯曽崻偲偄偆岅偺堄媊偑偮偐傑傟偰偄側偗傟偽偦偙偵偼尷奅偑偁偭偰偦偺桳岠惈偼朢偟偄偺偱偁傞丅廬偭偰丄暯曽崻偲偄偆岅傪抦幆偲偟偰偄偐偵廂傔偰偄傞偐偑栤戣偱偁傞丅傕偪傠傫偦偙偵偼屄乆偺恖暔偵傛偭偰棟夝偺掱搙嵎偑偁傝丄懠偵傕旝柇側堘偄偑擣傔傜傟傞偙偲偑偁傞偱偁傠偆丅偮傑傝丄暯曽偺僀儊乕僕傪帩偪丄偦偺忋偱偐偮暯曽崻偺堄枴傪棟夝偟偰偄傞偐偳偆偐丄偁傞偄偼枖丄屆戙悢妛巎忋偺抦幆偺懳墳擻椡偑偁傞偐偳偆偐偲偄偆傛偆偵偱偁傞丅廬偭偰丄嫮惂揑偵妎偊偝偣傜傟偨寢壥偲偟偰丄娭楢偡傞抦幆梫慺傗抦幆宯楍丄抦幆懱宯偵嫮偄寢傃偮偒傪帩偰側偔側偭偰偄傞抦幆偼丄傑偝偵暵嵡抦偲偟偰擼撪偵棷傑傞傢偗側偺偱偁傞丅
丂偙偙偱巹偼丄抦幆偑暵嵡抦偵側傞偐妶惈抦偵側傞偐偺廳梫側暘偐傟摴偲偟偰丄媈栤丒栤偄偐偗偲偄偆宊婡偑惗偠丄偟偐傕偦傟偑妶偐偝傟傞偐偳偆偐偲偄偆栤戣偺廳梫惈偵拝栚偟傛偆丅
丂媈栤傗栤偄偐偗偼丄傑偝偵旕尵岅揑捈懺傪梙偝傇傝丄儃儎乕儞傪廫暘偵敪梘偝偣偰丄偦偺抦幆梫慺傗偦偺尵傢傫偲偡傞偲偙傠傪懆偊傛偆偲偡傞丅暿偺柺偐傜尵偊偽丄庒乆偟偄旕尵岅揑捈懺偲妶惈壔偟偨儃儎乕儞傪桳偟偨恖娫偼丄媈栤傗栤偄偐偗傪峴側偭偰丄姶惈媊憡偺枮懌傪摼傛偆偲偡傞偺偱偁傞丅偦偺夁掱偱夛壇偑懳墳偟丄妶惈壔偟偨巚峫妶摦偑揥奐偝傟傞丅嫵壢彂偺傛偆偵丄奜偐傜媈栤傪弌偟偰偁偘傞偙偲傕昁梫偱偁傞丅偟偐偟丄撪懁偵偍偄偰斀墳偟偰偙側偗傟偽丄偦傟偼扨側傞摎偊扵偟偱廔傢傞偟偐側偄丅
媈栤傗栤偄偐偗偼丄扨弮偵扨敪揑側抦揑梫慺傊偺摥偒偐偗偱偼側偄丅妶惈抦偼丄怴偨側抦傪寎偊傞偨傔偵丄媈栤傗栤偄偐偗偺巇曽偱丄偦偺抦偺梫慺偑懏偡傋偒庬暿敾掕傪峴側偆偲摨帪偵丄杮棃丄婛偵妉摼偝傟偨暿偺抦幆傪榑棟揑偵峔惉偝傟偨宍偱偦偺抦偺梫慺偵岦偐傢偣丄偦傟傪揔愗偵摫偄偰偔傟傞偺偱偁傞丅偙偆偟偰媈栤傗栤偄偐偗偼丄抦幆偑恀偺妶椡傪梌偊傜傟丄朙偐側撪梕傪摼偰妉摼偝傟傞偲偄偆堄枴偱丄旕忢偵廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偺偱偁傞丅廬偭偰丄拲擖幃嫵堢偑恖娫偺抦揑庡懱惈傪懜廳偟側偄峴堊偱偁傞偙偲偼柧偒傜偐偱偁傝丄偙偺庬偺嫵堢偑庒幰偺抦揑庡懱惈傪扗偆尦嫢偵側傞偙偲傕柧傜偐偱偁傞偲尵偊傛偆丅
丂偲偙傠偱丄暵嵡抦偱屌傔傜傟偨摢偼丄抦揑妶惈壔偑峴側傢傟偵偔偄偨傔丄媈栤傗栤偄偐偗偑嬯庤偱偁傞丅偦偟偰廳偄徢忬偵側傞偲丄妶惈抦傪庴偗晅偗側偄丅埆偄偙偲偵暵嵡偟偰偄側偄偲庴偗擖傟傜傟側偔側傝丄廔偄偵偼抦幆偦偺傕偺傪婖旔偡傞偙偲偵傕側傞偺偱偁傞丅妛峑傪弌偨傜杮傪撉傑偢丄峫偊傞偙偲傪偟側偄恖娫偼丄懡偐傟彮側偐傟丄暵嵡抦偺媇惖幰偵側偭偰偄傞偲尒傞偙偲偑偱偒傞丅
丂偙傟傜偺帠忣偐傜丄妶惈抦偑丄恖娫偺憂憿揑壜擻惈傪怢偽偟丄暔帠傪怺偔峀偔抦傞崻嫆偵側傞偙偲偑梊憐偝傟傞丅暵嵡抦偼丄旕忢偵嫹偄椞堟傪嶌偭偰偔傞偐傜丄幮夛揑偵棙梡偝傟傞偲戝曄婋尟偱偁傞偲尵偊傞丅偙偺栤戣傪峫偊傞偵偮偄偰偼丄抦偺塩堊偺杮幙傪扵偭偰傒側偗傟偽側傞傑偄丅
丂
丂乮拲侾乯杮榑偱偼恎懱偲怱丄惗柦偺杮幙偵娭學偡傞旂晢姶妎偺堄媊偵偮偄偰徻偟偔専摙偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偟偐偟丄師偺嬶懱揑側帠幚偼丄偙傟偐傜偺恖娫娭學傪峫偊偨傝丄尰戙恖偺昦棟傪夝寛偟偰偄偔忋偱傕娕夁偱偒側偄婎慴揑擣幆傪梌偊傞偙偲偩傠偆丅愭偢丄変乆偼丄嬻婥偵晀姶偱偁傞丅摿偵廘偄丄婥壏丄壏搙偵懳偡傞斀墳偼丄惗懚傪嵍塃偡傞偲偄偆堄枴偱丄嵟傕廳梫側丄戞堦媺偺姶妎嶌梡偲偄偭偰傛偄丅偙偺姶妎偼丄嬻婥傗嬻娫偺抦妎埲奜偵傕奼挘偝傟丄敾暿婡擻偑暋嶨偵敪揥偡傞丅偟偐偟丄偦傟偼敾暿婡擻偵棷傑傜偢丄撪晹抦妎偵偍偄偰擼傗恎懱慡懱偵夣丄晄夣偺姶忣傪梌偊傞宍偱敪揥偟偰偒偨丅堦斒偵丄惗暔偼恊偲偺愙怗傗摨椶偲偺愙怗偵偍偄偰帺屓偺惗懚偺婎斦傪抦傝丄偦傟傪妋曐偡傞杮擻傪帩偭偰偄傞丅恖娫偺応崌丄偦偺偙偲偵傛偭偰撈帺偺怱揑悽奅偑惗偠丄怱偺惉挿偺婎慴偑梌偊傜傟傞偺偱偁傞丅巹偼丄堦壠拞偑嬯偟傓乮曣恊偼嬯擸偟偰帺嶦乯廫巐嵨偺愡怘忈奞乮嫅怘徢偐傜夁怘徢傊岦偐偭偨乯偺彮彈傪娕偰偒偨偑丄偦偺巕偑堄幆奾棎偱朶傟弌偟婥傪幐偭偨帪偵丄摨偠擭偺巹偺柡偲堦弿偵斵彈偺榬傗庤傪堦帪娫埵偝偡傝懕偗偨偙偲偑偁傞丅偙偺巹偨偪偺峴堊偼丄嬌傔偰帺慠偱弶曕揑側巚偄傗傝傗摨姶傪帵偡垽忣峴堊偲偟偰峴側傢傟偨偨傔丄斵彈偺恎懱揑抦妎傪傕偭偰柍尵偺偆偪偵彮彈偵惛恄揑側埨傜偓傪梌偊傞偙偲偵側偭偨丅偩偐傜丄栚妎傔偨偲偒偺彮彈偼丄幚偵壐傗偐側昞忣傪偟偰偙偪傜傪尒偨丅巹偺尒傞偲偙傠丄斵彈偵偲偭偰晄岾偩偭偨偙偲偼丄偦偺傛偆側峴堊傪婜懸偱偒側偄椉恊偵堢偰傜傟偰偒偨偙偲偱偁傞丅晀姶側彮彈偵丄壠掚傗妛峑傗幮夛惗妶忋偺條乆側晄岾側帠忣偑廳側偭偨寢壥丄彮彈偼怱偺埨掕傪幐偭偰偟傑偭偨丅峏偵埆偄帠忣偑偁傞丅偙偺彮彈偺応崌丄惛恄娪掕傗僇僂儞僙儕儞僌丄僒僀僐僙儔僺僗僩偺帯椕媦傃嫮惂揑擖堾惗妶偑丄寢嬊恖娫揑愙怗偲偄偆嵟傕娞恡側壽戣偵墳偊傞揰偱丄廳戝側寚娮傪帩偮傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅怱傪栤戣偵偟側偑傜丄怱偵怗傟側偄懳墳偵廔巒偟偰丄偦偺巕偺惛恄傪愗傝崗傫偱偟傑偭偨偺偱偁傞丅偦偺堄枴偱丄偙偺庬偺惛恄揑僩儔僽儖偵偍偄偰偼丄壢妛偼丄傗偼傝恖娫傪戝愗偵偡傞垽忣偵敪偟側偄尷傝丄枮懌側寢壥傪惗傒弌偡偙偲偼側偄偲偄偆偙偲偑暘偐傞丅偦偺垽忣偺婎慴偵丄旂晢姶妎偑懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偼丄偙偺帠椺偑偼偭偒傝帵偟偰偄傞丅旂晢壢偱偼丄惛恄揑側僗僩儗僗偑旂晢偺條乆側僩儔僽儖偵尠傟傞偙偲傪栤戣偵偡傞偺偱偁傞丅旂晢偺僩儔僽儖偺傒側傜偢丄恖娫偦偺傕偺偺僩儔僽儖偵娮傜偣偰偼側傜側偄偺偱偁傞丅
|
|
戞擇復丂抦揑塩堊偺杮幙丂乮抦幆偺悽奅娤揑惈幙媦傃垽抦揑惈幙乯
丂丂丂抦偺巌椷僗僥僀僩丄婍夿抦丒恖娫抦丄曄懱妶惈抦丒恀惈妶惈抦摍偺栤戣
|
|
1966擭偺挊彂偱丄P.B.僐僾僯儞偼丄抦幆偼摿偵恖椶偺宱尡偵傛偭偰攠夘偝傟偰偄傞偲巜揈偟丄偄偐側傞抦幆傕捈愙揑側傕偺偲攠夘偝傟偨傕偺偲偺摑堦偱偁傞偲彂偄偨丅枖丄姶妎偲抦妎偼丄抦幆偺梫慺揑嵶朎偱偁傞偲偙傠偺敾抐偺宍幃傪偲傞偲偒偵偼偠傔偰丄抦幆偵側傞偲傕巜揈偟偰偄傞乮凱.凚.凨剙剚剘剏剘:凚剅剈則剈剘剏剈丂剅丂剗刾剛剓剝剏剝剟剝剓剠剱丂剆剘剙剝剈剙剕剙剆剏剱, 凨剏剈剅, 1966 :嘫亅俁) 丅屻幰偺栤戣偼丄暿偺婡夛偵榑偢傞偲偟偰丄慜幰偐傜偼丄攠夘偝傟偨抦幆偑堦偮偺幚懱傪帩偮奣擮偲偟偰掕棫偡傞帪丄偦偺撪梕偼掕媊偺宍幃偵傛偭偰宍偳傜傟傞偵偟偰傕丄寛偟偰偦傟偵恠偒傞傕偺偱偼側偄偲偄偆栤戣偑堷偒弌偝傟傛偆丅壗屘偐丅偦偺棟桼偼丄抦幆偲偼偁傞柧妋側椪奅慄偵傛偭偰宍偳傜傟偨姰寢偟偨屄暔偱偼側偔丄幮夛揑側婯栺傪桳偡傞偵偟偰傕壜擻懺偱偁偭偰丄懠偺抦幆偲榑棟揑宍幃傪拞幉偵條乆側偮側偑傝曽偱寢傃偮偄偰惉棫偟偰偒偨傕偺偱偁傝丄偦傟備偊丄偦傟帺恎偺拞偵丄怴偨側抦幆傪嶻傒弌偡曣懱偲偟偰偺椡傗丄摦婡偵側傞椡傪桳偡傞傕偺偱偁傞偐傜偱偁傞丅偦偺偙偲傪壜擻懺偲偄偆岅傪梡偄偰帵偟偰傕傛偄偱偁傠偆丅抦幆偑偦傟帺恎偲偟偰壜擻懺偱偁傞偐傜偙偦丄屄恖偵偍偄偰丄僀儊乕僕揑摥偒偐偗偑惗傑傟丄朙偐側姶惈媊憡傪梫媮偟偰偔傞偺偱偁傞丅廬偭偰丄暵嵡抦偑斀抦揑側惈幙傪帩偭偰偄傞偙偲偼媈偄摼側偄丅
丂僜僔儏乕儖偼丄尵岅婰崋偑奣擮偲挳妎塮憸傪寢崌偟偨湏堄揑側傕偺偱偁傞偲峫偊偨丅尵岅婰崋儗儀儖偱偺栤戣偲偟偰傕丄奣擮偁傞偄偼東栿壜擻側撪梕傪帩偮僔僯僼傿僄偼丄屄乆恖傪棧傟偰丄楌巎幮夛揑側丄宱尡揑側丄偁傞偄偼壢妛揑側撪梕偵傛偭偰堷偒弌偝傟棤晅偗傜傟偰偄傞偲偼尵偊側偄偩傠偆偐丅偦傟偑尵岅傗巚峫儗儀儖偵払偡傞偲丄抦幆偺栤戣偲偟偰丄傕偭偲暋嶨側宍偺栤戣偵側偭偰偔傞偙偲偼梕堈偵憐憸偱偒傞偱偁傠偆丅偙偺偙偲傪捛媶偡傞偲偒偵愭偢峫椂偺栐偺拞偵廂傔偰偍偔傋偒偙偲偼丄恖娫偑幮夛揑摦暔偱偁傞偲偄偆傛偔抦傜傟偨帠幚偱偁傞丅偦傟備偊丄幮夛娭學偺婎懱偱偁傝丄嵟傕尰幚揑側惗偺搚戜偱偁傞恖娫娭學偑丄憡屳偺僐儈儏僯儏働乕僔儑儞妶摦偵傛偭偰嬶尰偝傟傞偲偄偆栤戣傪峫偊側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偵娭偟偰偼婛偵懡偔偺媍榑偲尋媶偑堊偝傟偰偄傞丅偦傟備偊丄巹偼丄抦幆偺栤戣偲偟偰師偺懁柺偵尷偭偰榑偠傞偙偲偵偟傛偆丅
丂巹偼丄抦幆偲偦傟傪梡偄傞巚峫妶摦偼丄幮夛揑寢傃偮偒傪敪揥偝偣丄奜奅偲帺屓偵懳偡傞擣幆傪怺傔傞尰幚偺妶摦偵傛偭偰丄偦偺堄媊傪帵偡偲偄偆揰偵拲栚偟偰偄傞丅偮傑傝恖娫偑抦幆傪拁偊棙梡偡傞偲偄偆堄枴偼丄帺慠傗娐嫬傗幮夛傗恖娫偺偦傟偧傟偵娭偡傞抦幆偼傕偪傠傫丄偦傟偧傟偺彅娭學丄彅楢娭傪棟夝偡傞椡傪偮偗丄惗懚偡傞揰偵擣傔傜傟傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦偆偱側偗傟偽丄恖娫偼椶恖墡偐傜儂儌僒僺僄儞僗傊偲敪揥偟偰偙側偐偭偨偲尵偭偰傛偄偺偱偁傞丅恖娫偑恖娫偵側偭偨偲偄偆崻尦揑側堄枴偱丄恖娫偼扤偟傕丄昁偢帺屓偺惗懚偲惉挿偵婑梌偡傞僄僱儖僊乕傪丄懄偪懠偺恖娫丄幮夛丄巇帠丄巚憐丄娐嫬丄帺慠摍偵寢傃偮偄偰惗妶偡傞嫮偄巙岦惈傪帩偭偰偄傞偺偱偁傞丅廬偭偰丄偦傟傜偵婑梌偡傞堄幆傕廳梫偱偁傝丄偦偺巙岦惈傪崅傔傞偙偲偑丄恖偑恖偲偟偰曢傜偟傪敪揥偝偣傞廳梫側栚揑偵側傞偙偲偼娫堘偄側偄偲尵偊傞偺偱偁傞丅傕偪傠傫帺屓偵揔偝側偄傕偺傪攔愃偡傞偨傔偵丄抦幆偲巚峫妶摦傪妶梡偡傞偙偲偑偁傞偺偼尵偆傑偱傕側偄丅
丂偙偺傛偆偵峫偊傞偲丄巹払偼丄師偺傛偆偵抦幆偺堄枴偲偦偺偁傝曽傪嬦枴偟側偗傟偽側傞傑偄丅巹偺抦幆偼壗偵寢傃偮偒丄巹偺壗傪朙偐偵偟偰偔傟偰偄傞偺偐偲丅枖偦傟偑丄恖娫揑側傕偺偱偁傞偐偳偆偐丄峀偔恖椶偺岾暉偵峷專偡傞傕偺偱偁傞偐斲偐偲丅偙偺栤偄傪朰傟偰偟傑偆偲丄抦幆偼丄暥壔傪扴偆傕偺偱偼側偔側傝丄椶揑懚嵼偲偟偰偺惈幙傪幐偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅恖娫抦偱偼側偔側傞偺偱偁傞丅応崌偵傛偭偰偼丄嬌傔偰堦曽揑偱婋尟側孹岦偵棙梡偝傟偐偹側偄庛偝傪傕偮傕偺偵側傞偺偱偁傞丅
丂偙傟傜偺栤偄偵懳偟偰偼丄婍夿偺婡擻偵慻傒擖傟傜傟偨婍夿抦偱偼側偔丄恖娫偑帺暘偺婡擻偺拞偵偲傝擖傟偨抦幆偲偟偰偺恖娫抦傪栤偄丄偦傟偲偺崿摨傪旔偗偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅
丂偙偺媍榑傪堦曕恑傔傛偆丅恖娫抦偵偼丄抦傗抦揑妶摦傪巟偊丄偦傟傜傪僐儞僩儘乕儖偟丄塣梡偡傞栶妱傪壥偨偡抦幆偺儗儀儖偑宍惉偝傟偰偄傞偲峫偊傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆偐丅偦偟偰偦傟偼恖娫偺惗懚偺梸朷偲怺偔捠偠偰惉棫偡傞偙偲傪峫偊崌傢偣傞昁梫偑偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅巹偼偦偺偁傝曽傪抦偺巌椷僗僥僀僩偲尒側偟丄抦幆偺傛傝崻尮揑側棟夝偵摓払偝偣傞昁梫傪姶偠偰偄傞丅巹偺棟夝偡傞抦偺巌椷僗僥僀僩偼丄恖娫偺惗懚偑屒棫偟偰峴側傢傟傞偺偱偼側偔丄垽偲壏傕傝偲偄偆椡傪摼偰丄懠偺條乆側摦椡揑宊婡傪庢傝崬傫偱偄傞傕偺偲夝庍偝傟偰傛偄偱偁傠偆丅峫偊偰傒傟偽丄杮擻揑偲偼偄偊丄崅摍摦暔偵偍偗傞惗懚偺梸朷傕丄弶傔偼偟偭偐傝恊巕偺鉐偱寢偽傟偰偄傞偺偱偁傞丅恊巕偺鉐偑側偔丄曻傝弌偝傟偨巕偼堢偮偙偲偑偱偒側偄丅恖娫偵偍偄偰偼丄怘椏傗廧傑偄偑梌偊傜傟傛偆偲傕丄恖偲偺惛恄揑娭傢傝偑庛偗傟偽丄恖娫傜偟偄姶忣傪堢傓偙偲偼偱偒側偄丅恖娫偑晐偄偺偼丄恖娫偑恖娫偱側偔側傞偙偲偑偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅婼傗壓摍摦暔暲偵側傞偙偲傕壜擻偱偁傞偺偑丄恖娫側偺偱偁傞丅偩偐傜偙偦丄抦偺巌椷僗僥僀僩傪巹払偼栤戣偵偟側偗傟偽側傜側偄丅椣棟妛偼丄偦偺巌椷僗僥僀僩偺偁傝曽傪挿偄娫栤偄懕偗偰偒偨偲尵偆偙偲偑偱偒傞偱偁傠偆丅巹偼偙偙偱丄抦幆榑偲偟偰丄恖娫偺擣幆峔憿偺拞偱偦傟傪栤戣偵偡傞偺偱偁傞丅
丂廬偭偰巹払偼丄師偺傛偆偵抦幆偺杮尮揑惈幙傪怺傔傞偙偲偑偱偒傞丅懄偪丄戞堦偵忋婰偺堄枴偱恖娫偺抦幆偼丄堦偮偺昁慠偲偟偰丄恖娫偲恖椶偺岾暉偵岦偐偭偰丄峀偄悽奅娤偺拞偱帋偝傟傞偩偗偺峔憿偲婡擻傪帩偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟傪抦幆偺悽奅娤揑惈幙偲尵偭偰偍偔丅偙偺惈幙偵偼丄恖娫揑側枖恖椶揑側岾暉傊偺棟夝偲摦婡偑娷傑傟偰偄傞丅戞擇偵丄抦幆偼丄抦偺崻嫆偵岦偐偄丄帺傜傪婎慴晅偗偰偄偔偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟傪抦幆偺垽抦揑乮揘妛揑乯惈幙偲屇傫偱偍偙偆丅榑棟惈丄壢妛惈偼偙偺惈幙傪扴偆廳梫側拰偲偟偰棟夝偝傟傞丅抦幆偺巌椷僗僥僀僩偼丄偙傟傜偺梫審傪杮尮揑側梫惪偲偟偰庴偗偲傔傞応偱偁傞丅廬偭偰丄巹払偼偙偺峔憿偲婡擻傪偙偦堢偰摥偐偣偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅巌椷僗僥僀僩偑嬌傔偰曃偭偨柦椷傪弌偡傛偆偵側傞応崌偼丄傕偪傠傫偦偺恖娫偺抦偺宍惉偲恖娫宍惉偲偺娭楢傪栤傢側偗傟偽側傜側偄丅偦偺曃偭偨搚戜偵棫偭偰偟偐婡擻偟側偔側傞抦偼丄曄懱抦偲屇傇傋偒抦揑忈奞傪旐偭偰偄傞偲尒側偣傞偺偱偁傝丄偙傟偼妶惈偟偰偄偰傕嫋梕偡傞偙偲偺偱偒側偄抦幆側偺偱偁傞丅摨條偵敪揥偺夎傪暵偞偝傟偰偄傞暵嵡抦偵偍偄偰丄廬弴偵偁傞庬偺斀恖娫揑屇傃偐偗偵墳偊傞曄懱壔偟偨暵嵡抦乮曄懱暵嵡抦乯傕廫暘寈夲偝傟丄偦傟偵娮傜側偄傛偆偵偟側偗傟偽側傜側偄丅
丂偙偙偵偍偄偰丄妶惈抦偑丄抦幆偺悽奅娤揑惈幙偲垽抦揑惈幙傪帩偭偰嬌傔偰惗嶻揑側妶摦傪峴偆恀惈妶惈抦偱側偗傟偽側傜偢丄暵嵡抦偺傒側傜偢丄曄懱妶惈抦傕寈夲偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偑柧傜偐偵側偭偨偲巚偆丅
丂偟偐偟堦斣偺栤戣偼丄抦慡懱傪摫偔巜椷僗僥僀僩偺宍惉偱偁傞丅巜椷僗僥僀僩偙偦偼丄恖娫偺抋惗偐傜偺嫵堢傪幉偵宍嶌傜傟偰偄偔偺偱偁偭偰丄嫵堢偺廳梫惈傪寛掕揑偵偡傞傕偺偱偁傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅壗屘側傜丄嫵堢偑丄宆捠傝偺恾幃庡媊偱丄埫婰庡媊偱丄壽戣庡媊偱丄僥僗僩庡媊偱偲偄偆傆偆偵嫮惂偝傟偨傕偺偱偁傞偲丄偛偔堦晹偺幰偺傒偑朙偐側抦幆傊岦偐偆偵偲偳傑偭偰偟傑偆偐傜偱偁傞丅偦偟偰戝懡悢偺恖乆偑丄巜椷僗僥僀僩傪丄抦幆偺扵媶偵傛偭偰宍惉偡傞偙偲崲擄偵側偭偰偟傑偆偐傜偱偁傞丅偦偙偱扤偱傕宱尡偑偁傞偱偁傠偆堦偮偺椺傪庢傝忋偘偰丄嫵堢偺廳梫側栶妱偵偮偄偰峫偊傞偙偲偵偡傞丅
丂彫偝偄巕偑乽壗屘乿傪楢敪偟偰恊傪崲傜偣傞偙偲偑偁傞丅壗屘偲偄偆栤偄偼丄巕偳傕偑恖椶偲偄偆椶揑懚嵼偱偁傞壗傛傝偺徹嫆偱偁傞偲偼尵偊側偄偩傠偆偐丅晄巚媍偵巚偆偦偺婥帩偪偑傑偝偵恀惈妶惈抦偺曣懱偱偁偭偰丄壗屘偲栤偆偙偲偼丄嬌傔偰廳梫側抦揑僗僥乕僕偱偁傞偲偼尵偊側偄偩傠偆偐丅偦傟偼丄暯斅偱偼側偔丄惗偒傞偲偄偆妶椡偲偮側偑偭偰偄傞偺偱偁傞丅偦偺揰偑巜椷僗僥僀僩宍惉偵偍偄偰戞堦偵娞恡側偲偙傠偱偁傞偲巹偼峫偊偰偄傞丅懄偪偦傟偼恖娫嫵堢偺戞堦埵傪愯傔傞傋偒忦審偱偁傞丅
丂師偵廳梫側偙偲偼壗偐丅偦傟偼丄抦幆偑丄恖椶偺挿偄楌巎傪攚晧偭偰偍傝丄壛偊偰偦傟偧傟偺柉懓偺楌巎傗揱摑傪攚晧偭偨傕偺偱偁傞偲偄偆揰偵娭傢偭偰偄傞丅妋偐偵抦幆偺拲擖庡媊偼傛偔側偄寢壥傪傕偨傜偡丅偩偐傜偲偄偭偰偦偺埖偄傪妛廗幰偺帺桼偵擟偣傞偙偲偱丄挿偄楌巎傪捠偠偰妉摼偝傟偰偒偨抦揑塩傒偑媧廂偱偒傞傢偗偼側偄丅抦幆偵偼抦幆偺丄椺偊偽壢妛偲偄偆宍幃偲忦審傪枮偨偡拋彉偑昁梫偱偁傞丅榑棟偑昁梫偱偁傝丄抜奒傕峫椂偝傟側偗傟偽側傜側偄丅曽朄榑傕偦偺堦偮偱偁傞偑丄栤戣偼丄偦傟傜偑揔愗偱偁傞偐偲偄偆懁柺偲丄妛廗幰偺帺敪揑側敪憐傗媈栤偑妶偐偝傟揥奐偝傟傞偐偲偄偆懁柺偺椉曽偵傑偨偑偭偰偄傞丅屻幰偵娭偟偰偼丄峫偊傞備偲傝偲偒偭偐偗傪梌偊傞偙偲偑娞恡偱偁傞丅宆捠傝偺恾幃庡媊丄埫婰庡媊丄壽戣庡媊丄僥僗僩庡媊側偳偼丄梫偡傞偵偦偺備偲傝偲偒偭偐偗傪梌偊偢偵丄柍棟傪偝偣傞偲偄偆偩偗偺偙偲側偺偱偁傞丅婔懡偺椺偑帵偡偲偍傝丄偦偺偨傔偵丄懡偔偺恖乆偵偲偭偰偼丄奺恖偑帩偮恀偺擻椡偲壜擻惈傪堷偒弌偝傟偢丄傓偟傠斀懳偵戝偄偵捵偝傟偰偒偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞偱偁傠偆丅
丂抦幆偼丄巜椷僗僥僀僩偺宍惉偲偁偄傑偭偰丄夛壇偝傟偨妶惈抦偲偟偰丄偦偺悽奅娤揑惈幙媦傃垽抦揑惈幙傪崻杮偵偟偰妶偐偝傟側偗傟偽側傜側偄丅巹偼偙傟傜偺棟夝傪婎偵丄偙傟偐傜愭偺帪戙傪丄恖椶慡懱偺夝曻偲敪揥偵岦偗偰妶摦偟丄惗妶偟側偗傟偽側傜側偄偲峫偊傞偺偱偁傞丅 |
|
枹掕峞
|
丂擇廫悽婭偺採婲偟偨栤戣偼寁傝抦傟側偄偔傜偄廳戝側恖椶巎偺壽戣偱偁傝丄巹払偼偦偺杦偳傪夝寛偟偰偄側偄丅
丂擇廫悽婭偺慜敿偼偡傋偰丄壗偲尵偭偰傕悽奅戝愴偺帪戙偱偁偭偨丅偦偺屻敿傕椻愴峔憿傪幉偵儀僩僫儉愴憟傪偼偠傔丄庡偵偼帒杮庡媊幮夛懱惂偲幮夛庡媊幮夛懱惂偺懳寛傪傔偖傞懳寛偺帪戙偱偁偭偨偲尵偭偰傛偄偱偁傠偆丅嫄戝側帒嬥偲孯帠椡傪攚宨偵丄廃摓側悽奅愴棯壓偵偁偭偰丄偦傟偼巚憐丄柉懓丄廆嫵摍條乆側懳棫偺宍偱弌尰偟偨丅偦傟傜偼僷儚乕億儕僥傿僢僋僗傪柍帇偟偰偼棟夝偱偒側偄偟丄惃椡傪帩偮偙偲傕偱偒側偄偲尵偆偙偲偑偱偒偨丅偙偺偙偲傪峫偊傞帪丄巹偼丄掗崙庡媊崙壠寶愝傪巊柦偲偟偨帒杮庡媊偺擇廫悽婭宆揥奐丄幮夛庡媊妶摦偺廳戝側宱尡丄壢妛偲媄弍偺敪揥偲偦偺廳戝側栶妱傪巚偄晜偐傋傞丅偦偟偰丄愴憟丄帒杮丄巗応丄柉懓丄廆嫵丄娐嫬丄僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞摍乆丄條乆側尵梩偱擇廫悽婭偵婲偒偨帠暱傪巚偄晜偐傋傞丅
丂偦偺傛偆偵偟偰丄抦幆偺栤戣偲偟偰丄巹偼丄僼僢僒乕儖偑嵟屻偵榑媦偟偨惣墷揑抦幆偺婋婡偺栤戣傪峫偊傞偺偱偁傞丅廃抦偺傛偆偵丄戞堦師悽奅戝愴偼丄僼僢僒乕儖偵懳偟偰嬌傔偰廳戝側丄揘妛忋偺僠儍儗儞僕傪梫媮偟丄斵偺尰徾妛偵戝偄側傞巊柦偲妶椡傪梌偊偨丅偦傟偑僼僢僒乕儖斢擭偺戝嶌偱偁傞乽儓乕儘僢僷彅妛偺婋婡偲挻墇榑揑尰徾妛乿偱榑偠傜傟偨悢乆偺栤戣偱偁傞偺偱偁傞丅乮Edmund丂Husserl丗The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology乯
乽儘僢僋偑彅妛傪怱揑嶌嬈偲峫偊偰乮偨偲偊斵偑丄偁傑傝偵傕屄恖偺怱偺拞偱婲偙傞偙偲偵娽傪岦偗偡偓偨偵偟偰傕乯丄偄偨傞偲偙傠偱偦偺婲尮偺栤偄傪採婲偟偨偺偼妋偐偵傕偭偲傕側偙偲偱偁傝丄惓偟偄偙偲偱偁偭偨丅側偤側傜丄嶌嬈偼側傫偲偄偭偰傕丄偦傟傪悑峴偡傞偼偨傜偒偐傜偺傒棟夝偝傟偆傞傕偺偩偐傜偱偁傞丅乮拞棯乯偄偆傑偱傕側偔僇儞僩偵偟偰傕丄儘僢僋偺怱棟妛偵柍憿嶌偵偲傝偮偄偨傢偗偱偼側偐偭偨丅偟偐偟丄偩偐傜偲偄偭偰丄儘僢僋偺怱棟妛揑丄擣幆榑揑側栤戣愝掕偺堦斒揑側揰傪堩偟偨偺偼惓偟偐偭偨偱偁傠偆偐丅僸儏乕儉偐傜巋寖偝傟偨栤戣傪偡傋偰丄偝偟偁偨偭偰怱棟妛揑側栤戣偲偟偰偲傜偊偨偺偼惓偟偐偭偨偱偁傠偆偐丅乮拞棯乯妛堦斒偼丄恖娫偺嶌嬈偱偁傞偙偲丄偡側傢偪丄偦傟帺恎悽奅偺偆偪偵丄堦斒揑宱尡偺偆偪偵偁傞恖娫偺嶌嬈偱偁傞偙偲丄偦偟偰偙偺嶌嬈偼丄棟榑揑偲屇偽傟傞偁傞庬偺惛恄揑宍惉懱偵岦偗傜傟偰偄傞幚慔揑嶌嬈偺堦庬偱偁傞偙偲偑峫椂偝傟側偗傟偽側傜側偄丅偁傜備傞幚慔偲傂偲偟偔丄偙偺嶌嬈傕傑偨丄峴堊幰帺恎偵傕堄幆偝傟偰偄傞屌桳偺堄枴偵偍偄偰丄偁傜偐偠傔梌偊傜傟偰偄傞宱尡偺悽奅傊娭學偟丄傑偨摨帪偵偦偺宱尡偺悽奅偵曇傒崬傑傟偰偄傞偺偱偁傞丅乿乮戞31愡乯
崱傗僐儞僺儏乕僞傪庡摴嬶偲偡傞僨乕僞庡媊丄忣曬棙梡偺帪戙偱偁傞丅愭恑彅崙偵偍偄偰偼丄妋偐偵壢妛偲媄弍偺椡偼丄幮夛惗妶偺嬿乆偵帄傞傑偱暍偭偰偒偰偄傞丅堛椕峴堊堦偮尒偰傕偦偺壎宐偼寁傝抦傟側偄傕偺偑偁傞丅墦妘抧傗旕忢偵曋偺埆偄応強偱傕丄拞墰偲捈寢偟偰丄壜擻側尷傝庤弍傪娷傓桳岠側帯椕偑壜擻偵側偭偰偒偰偄傞偺偩丅
丂偟偐偟丄偩偐傜偲偄偭偰丄僼僢僒乕儖偺偙偺巜揈偼慡偔捖晠偱屆廘偄傕偺偱偟偐側偔側偭偨偱偁傠偆偐丅偄傗寛偟偰偦偆偱偼側偄丅傓偟傠僼僢僒乕儖偼崱擔偵帄傞曄壔偺夁掱傪梊婜偟偰丄屄恖偲恖娫傪庢傝栠偡妛栤傪寶愝偟傛偆偲偟偨偺偱偁傞丅斵偺媍榑偺崻掙偵棳傟傞丄峀偄恖娫妛傊偺娭怱傪尒幐偭偰偼側傜側偄偲巹偼峫偊傞丅僼僢僒乕儖偑丄斵偺尰徾妛偵偍偄偰丄幚徹壢妛丄偦偺戙昞偲偟偰偺暔棟妛揑媞娤庡媊傗帺慠偺悢妛壔丄悢妛壔偝傟偨帺慠壢妛傪斸敾偟偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅斵偼丄摿偵儓乕儘僢僷揑妛栤偺榑棟偑悽奅傪岆傜偣傞崻杮揑寚娮傪帩偭偰偄傞偲懆偊偨偺偱偁傞丅偙偺帪斵偼丄恖娫偲屄恖傪尒幐偆偙偲側偔丄傓偟傠偙傟傪抦揑側妛栤揑栤戣偺婎慴偵偍偄偰丄栤戣傪懆偊側偍偦偆偲偟偨偺偱偁傞丅変乆偼偙偺僼僢僒乕儖偺採婲傪丄扨側傞妛攈偺庡挘偲偟偰寉帇偟偨傝丄崱擔偱偼暔棟妛揑媞娤庡媊摍偼偲偆偵崕暈偝傟偨屆偄媍榑偩側偳偲尵偭偰嵪傑偡傋偒偱偼側偄丅偦偺寢壥偲偟偰恀幚廳偄尰幚揑壽戣偐傜摝旔偡傋偒偱偼側偄丅
丂偙偙偱偼丄儓乕儘僢僷揑妛栤傗抦惈偑偳偆偱偁傞偐偲偄偆栤戣傪棫偰傞昁梫偼側偄丅偟偐偟丄抦幆偼恖娫惈偲愗傝棧偟偰偦傟帺懱偲偟偰偺撈棫惈傪帩偮偲偐丄偁傞偄偼恖娫惈傪幐偆偙偲偑偁傞偺偐偲偄偆栤偄傪棫偰傞偙偲偼偱偒傞丅偦傟偼昁偢偟傕暵嵡抦偵娭偡傞偙偲偩偗偱偼側偔丄妶惈抦偵懳偟偰傕尵偊傞偙偲偱偼側偄偩傠偆偐偲栤偆偙偲偑偱偒傞丅
丂挻墇揑側堄枴偱丄抦幆偼丄堦恖堦恖偺恖娫偵懳偟偰撈棫偟偰偄傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅悢妛忋偺抦幆偼丄偡傋偰偺恖偵奐偗偰偄傞丅惗暔妛傕摨偠偱偁傞丅偡傋偰偺妛弍揑抦幆偼丄偡傋偰偺恖娫偑妛廗偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅巗応宱嵪偺抦幆偼丄夛幮傗婇嬈偺宱塩偵寚偐偡偙偲偑偱偒側偄傕偺偱偁傞偟丄僐儞僺儏乕僞乕偺媄弍傗抦幆偼丄崱傗懡偔偺恖偺媮傔傞偲偙傠偲側偭偰偄傞丅椬嬤強偵廧傓恖乆偑梌偊傞偦偺恖乆偺抦幆傕偁傞丅昦婥傗帠屘偺帪偼偳偆偟偨傜傛偄偐偲偐丄怘帠偺偲傝曽丄嶌傝曽偺抦幆傗媄弍傕偁傞丅偙偆彂偄偰偔傟偽愗傝偑側偄偙偲偱偁傞偑丄偙傟傜偺抦幆偡傋偰傪堦妵偟偰丄偡傋偰偺抦幆偵恖娫惈傪栤偆偙偲偑偱偒傞偐丄偁傞偄偼恖娫惈偲偼撈棫揑偐偲栤偆偙偲偼廫暘壜擻偱偁傞丅偦偟偰偦偺昁梫偼廫暘偵戝偒偄丅
丂栤戣偼偦偺抦幆偺崻偱偁傞丅抦幆偦傟帺懱偼晛抜偐傜偦偺崻偲嫟偵棫偪弌偱傞偺偱偼側偄丅偦偺帪偦偺帪偺昁梫偵嵍塃偝傟偰偄傞偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅偟偐偟丄偦傟偑巜椷僗僥僀僩偵偮側偑偭偨妶惈抦偱偁傟偽丄偦偺帪偦偺帪偺昁梫傊偺懳墳偵傕嵎偑惗偠傞丅枖丄抦偺杮幙偺堦偮偵崻尮揑側傕偺傊偺捈寢偱偼側偔丄恖娫偺擔忢惗妶傪巟偊傞偨傔偵棙梡偝傟傞偲偄偆栶妱偺偁傞偙偲傕峫椂偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅抦幆偺幚梡揑懁柺偼丄learning偲偄偆尵梩偱帵偝傟傞丅偟偐偟偦傟偲偰傕丄夵傔偰偁傞栤偄偐偗傪峴側偊偽丄懠偺條乆側抦幆傗昁梫偲寢傃偮偄偰怴偨側擣幆偵帄傞偙偲偑壜擻偱偁偭偰丄偄傢備傞妛弍揑側抦幆偺傛偆偵丄崻尮揑側棟夝偵捈愙揑偵寢傃偮偔偙偲傪昁梫偲偟丄怴偨側妶惈壔傪峴側偭偨傝丄廳梫側巚峫妶摦傪揥奐偡傞梫慺偵側傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偙偲偵夁偓側偄丅
丂偦偙偱丄崱擔偺俬俿乮Information Technology乯傪婎幉偲偡傞忣曬壔幮夛偵偍偗傞恖娫偑丄偄偐偵抦幆偵懳墳偡傞偺偐偲偄偆栤戣傪峫偊傞昁梫偑惗偠傞丅
丂堦斣栤戣側偺偼丄忣曬偲偄偆栐偺栚偑僌儘乕僶儖偵峀偑傝丄嫄戝壔偟嵶枾壔偡傞帪戙偵偁偭偰丄偟偐傕幮夛傗婇嬈傗寢幮傗屄恖偺棙奞偑偙偺娭學偺拞偱嵍塃偝傟傞偲偄偆帪戙偑朘傟偨尰戙偵偍偄偰丄朿戝壔偟偨抦幆偺learning揑懁柺偵恖偺娭怱偑堏傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦偺偨傔偵丄抦幆帺懱偑僎乕儉壔偟丄椣棟揑壙抣傗愑擟偲偄偆傕偺偐傜棧傟偰懚嵼偡傞傛偆偵側偭偰偒偰偄傞偲偄偆偙偲側偺偱偁傞丅
丂偄傗偦偺媍榑傪峴側偆慜偵丄擇廫悽婭偺庛揰傪傕偆彮偟尒偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偼丄愴憟傗嵎暿偵偮側偑傞巚憐偲丄恀偺暯摍傪栚巜偡偼偢偺嵍梼揑妶摦偺彮側偐傜偸晹暘偑丄撈嵸傗梷埑傪庡偲偟偨旕忢偵尃椡揑側憡杄偵偍偄偰恑傔傜傟偰偒偨偙偲偵懳偡傞抦幆偺栶妱偲偄偆栤戣偱偁傞丅
丂
丂忣曬媄弍偺棙梡偵偍偄偰媫懍側曄杄傪惉偟悑偘偰偒偨擔杮偵偍偄偰偼丄嫵堢偺柍椡偝傗崿棎傪杦偳偡傋偰偺恖偑姶偠偰偄傞偲巚傢傟傞埵側偺偵丄抦幆奒媺偺憡摉晹暘偼抦揑廩懌傪枮偨偡偙偲偵绨恑偟偰巭傑側偄丅恖娫揑偁傞偄偼幮夛揑偵崲擄側栤戣傕丄僐儞僺儏乕僞乕偺儗儀儖偱僨乕僞傪偲偭偰暘愅偟丄暘椶偟丄恾幃揑側姰寢惈傪摼偰偐傜帺怣傪傕偭偰寢榑傪弌偡丅斀柺丄抦幆偺捛偄偐偗偭偙偺傛偆側僎乕儉傗丄偍偟傖傟偱婥偺偒偄偨尵梩傪楳傇偙偲偵姷傟偰偟傑偭偰偄傞丅 |
|
戞巐復丂21悽婭偵偍偗傞婋婡偲攋嬊偵懳偡傞妶惈抦偺栶妱 |
枹掕峞
|
丂恖椶偵偲偭偰丄嵟戝偺婋婡偼妀愴憟偱偁傝丄暥帤捠傝悽奅偺暔棟揑攋夡偲徚柵偱偁傞丅
丂偟偐偟丄巹払偑尰幚栤戣偲偟偰丄擔忢揑偵惗妶儗儀儖偱偦偺埖偄偲懳張偵崲傞廳戝栤戣偼丄忣曬壔幮夛傪偄偐偵惗偒丄偄偐偵朷傑偟偄宍偵摫偔偐偲偄偆偙偲偱偁傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅偦傟偼摿偵丄忣曬壔幮夛偺嵟愭抂傪憱傞擔杮偵偍偄偰丄廳戝側嫵孭偵側偭偰偄傞丅
丂擔杮偵偍偄偰丄旕忢側恖娫偺戅攑偲峳攑偑恑傫偱偄傞偙偲偼師偺帠椺傪尒傞偩偗偱廫暘偱偁傞丅懄偪丄堦壄巐愮枩偺恖岥傪書偊傞擔杮偼丄敧妱偑偨偑搒夛偵廧傓偲尵傢傟偰偄傞偑丄帺桼尃傪丄椺偊偽尵榑偺帺桼傪丄尃椡偵傛傞恖柉偺梷埑傊偺楌巎揑掞峈偲偟偰丄幮夛偺昳埵傪崅傔丄曢傜偟傗偡偄恖娫揑幮夛偺寶愝偲偟偰懆偊傞晽挭偼嬌傔偰庛偄傕偺偵側偭偰偄傞丅偦偺巚憐揑攚宨偺側偝偼丄摿偵1960擭戙偺崅搙惉挿婜埲棃丄応摉偨傝揑側寉敄暥壔傪儅僗僐儈偺拞墰偵埵抲偝偣傞傑偱偵偟偰偟傑偭偨丅儅僗僐儈偼丄帇挳棪傪捛偄丄傕偲傕偲娒偄朄偺偓傝偓傝傑偱怘偄崬傫偱丄朿戝側揹椡傪擔栭徚旓偝偣偰偄傞偺偱偁傞丅椺偊偽丄攕愴婰擮擔傗巕偳傕偺擔偵丄偦傟偵憡墳偟偄斣慻偑偳傟偩偗慻傑傟偨偐傪尒傟偽丄偦偺暥壔揑悈弨偼堦栚椖慠偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅偦偺戙傢傝偵棳偝傟傞傕偺偼丄愒棁乆偱業崪側惈揑夋憸傪娷傫偩楒垽傗惈偵娭偡傞傕偺偱偁偭偨傝丄懠垽傕側偄偍挐傝傗僪儔儅偱偁偭偨傝丄擔忢揑側忣曬傗怘傋摴妝丄峴妝偺椶偺斣慻偱偁傞丅彫妛惗偺娽偵傕旘傃崬傓宍偱丄懎埆側廡姧帍偺幨恀擖傝峀崘偑揹幵偺偄偨傞強偱尒傜傟丄怴暦偵嵹偣傜傟偰偄傞丅塮憸傗榖戣偑掅懎壔偡傞偙偲偵敽偭偰丄旕忢偵抳柦揑側栤戣偵側偭偰偄傞偺偼丄尵岅偺斱懎壔偲掅懎壔丄偦偟偰朶椡壔偺栤戣偱偁傞丅挿偄楌巎傪捠偠偰丄尵岅偲尵岅昞尰椡偼丄幮夛惗妶偺拞偱丄惗妶偵枾拝偟偰廗摼偝傟偰偒偨傢偗偱偁傞丅廬偭偰丄擔杮偵偍偄偰傕丄堦斒壠掚偱堢偪丄堦斒揑幮夛惗妶傪憲傞応崌丄尵岅傕偦偺惗妶傪斀塮偡傞傕偺偲尵偆偙偲偑偱偒偨丅壠掚傗妛峑偼丄朶椡揑偱斱懎側尵岅惗妶傪墦偞偗傞偙偲偑偱偒偨偺偱偁傞丅偲偙傠偑丄尰嵼丄斱懎偐偮朶椡揑側尵岅偲昞尰偼丄慡崙偄偨傞偲偙傠偱偼偽偐傞偙偲側偔壠掚偵擖偭偰偒偰丄庒幰偑墭愼忬懺偵娮偭偰巚峫椡傪幐傢偝傟偰偍傝丄戝恖傕抦傜偢抦傜偢杻醿偟丄撆偝傟偰偒偰偄傞偙偲偼斲掕偡傞偙偲偑偱偒側偄丅傕偪傠傫嶰乑擭埲忋慜偵偼戝庤傪怳偭偰嫋偝傟傞偙偲偱偼側偐偭偨偺偱偁傞偑丄旕忢側惃偄偱懎埆壓偲掅懎壓偑恑傒丄擔杮偼偐側傝偺晹暘偑偦傟偵姷傟愗偭偨忬懺偱偁傞偲尵偊傞偺偱偁傞丅峀偔崅搙側嫵堢傪梌偊傜傟丄晉傕偁傞擔杮恖偺幮夛揑堄幆傗惛恄揑婡擻偺掅壓偼丄旕忢偵廳戝側幮夛栤戣偱偁傞丅
丂偦偺揟宆揑側敳偒嵎偟側傜偸徹嫆傪堦偮徯夘偟側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偼惵彮擭偺斊嵾孹岦偱偁傞丅
丂捈柺偡傞廳戝帠偼丄僐儞僺儏乕僞傪幉偲偡傞媄弍捠怣妚柦偺栤戣偱偁傞丅幮夛偼丄崙嵺揑丄抧媴揑婯柾偱摦偔偩偗偱偼側偔丄傑偝偵枹慭桳偺曄姺揰偵棫偭偰偄傞偺偱偁傞丅婯柾偩偗偱偼側偄丅曄壔偺巇曽帺懱偑枹慭桳側偺偱偁傞丅椺偊偽奒媺摤憟偵傛傞妚柦偲偄偆曄壔傪変乆偼傕偆壗悽婭偵傕傢偨偭偰宱尡偟偰偒偰偄傞丅枖嶻嬈妚柦偵傛偭偰悽奅偑寑揑偵曄壔偟偨偙偲傪棟夝偟偰偄傞丅偦傟偵敽偆恖娫偲幮夛偺曄杄偵偮偄偰傕丄妛傃偆傞傢偗偱偼側偄偐丅
丂偟偐偟丄偳偆偱偁傠偆偐丅崱堷偒婲偙偝傟偰偄傞忣曬媄弍偺悽奅巟攝偼丄嶻嬈妚柦偺墑挿慄忋偱懆偊偒傞偙偲偑壜擻側栤戣偱偁傠偆偐丅
|
|
|
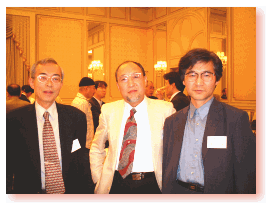 |
丂丂丂丂丂丂丂丂揘妛幰偺桭恖偨偪偲
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嵍乯丂搰嶈棽偝傫丗堦嫶戝妛嫵庼
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮塃乯丂娾嵅栁偝傫丗堦嫶戝妛嫵庼
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嶣塭乯屆栁揷岹偝傫丗堦嫶戝妛嫵庼
俀侽侽係擭俆寧俀俀擔丂擔杮揘妛夛憤夛乮奐嵜撿嶳戝妛丒柤屆壆乯崸恊夛応偵偰
亀擔杮揘妛夛亁乧乧擔杮偺揘妛尋媶偺敪揥偲丄尋媶幰娫偺岎棳傪妶敪壔偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞
慡崙婯柾偺妛夛丅
|
|
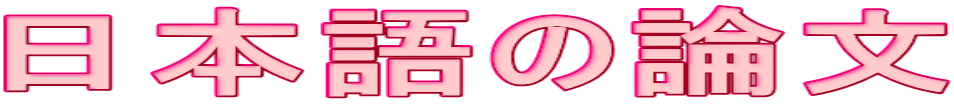
 僩僢僾儁乕僕傊傕偳傞
僩僢僾儁乕僕傊傕偳傞